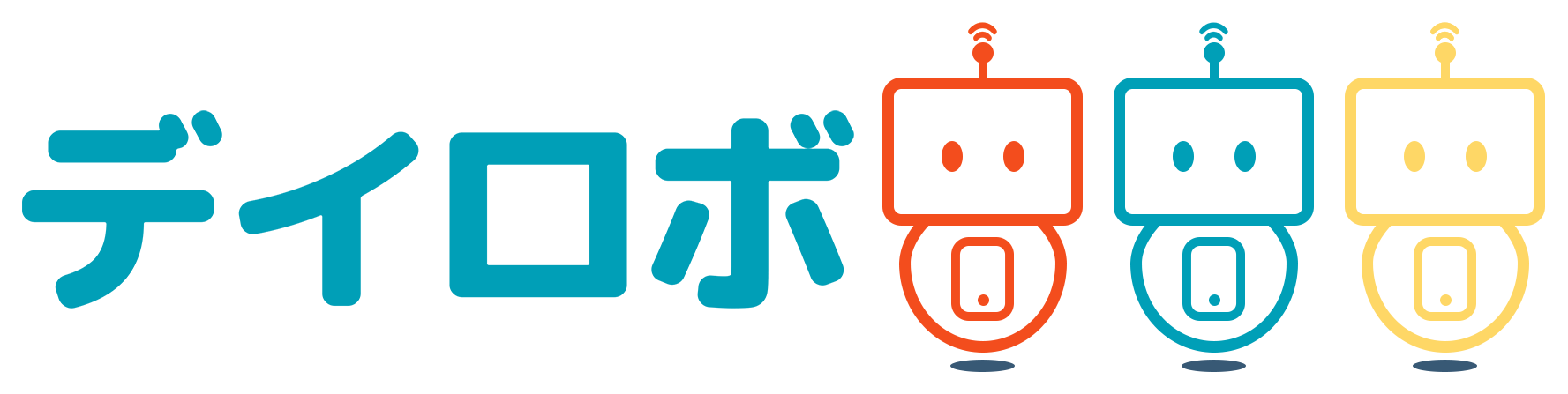さて、最後に「デイロボ」で最も重要な機能についてご説明しましょう。
これまでお話ししてきたように、デイロボを使うとこれまで「紙とペン」だった記録のほとんどが「クラウドとスマホ」になります。しかしメリットはそれだけではありません。
現在の「紙」の記録は、法的に5年間の保存が義務付けられていますが、逆に言うと「5年経ったら捨てられ」ています。つまり小学6年生になったら1年生のものから捨てられ始めるわけで、結局、大人になった時に「子供の頃の記録は何も残っていない」のです。
デイロボを導入すれば、それらの記録がなくなってしまうことは二度となく、さらに保護者や保護者から許可を得た事業所の職員などが過去の記録から欲しい情報を検索できるようになります。たとえば成人後に「小学校1年生の頃の夏休みには何が起こってた?」というようなことも簡単にわかるようになるのです。
そして子どもたちが卒業後、これが大いに生きてきます。
現在、成人の障害者の勤務先では「子供の頃どんな子だったのか知りたい」という情報ニーズが高まっています。作業所でいろいろな作業をする際、あるいはグループホームなどで他の人と一緒に暮らしていく時に、どんな事に気をつければよいのか、本人にとって何が困りごとで何が快適なのかを、現場職員は深く知りたいと思っているからです。
しかし現在「過去(子供の頃)の記録」は、学校から「個別支援計画書」が一枚もらえればいい方で、放デイでの連絡帳や個人記録が伝わることはありません。保護者もマメに記録をつけていなければ、記憶は結構曖昧になっていることが多く、面談だけでは必要な情報をすべて伝えることはできません。
放デイには小1~高3まで最大12年間通います。デイロボはこの期間の記録情報をいわばデータベース化します。そして将来、その子が大人になって社会で生きていく時に、保護者はもちろん、その時々の周囲の支援者が必要に応じて情報を引き出し、例えば医療のカルテのように、あるいは電化製品の「取説」のように使うことができます。